活動報告/クオリア京都
第11回クオリアAGORA_2014/ディスカッション
≪こちらのリンクよりプログラムごとのページへ移動できます≫
ディスカッサント
佛教大学社会学部教授
高田 公理 氏
同志社大学大学院総合政策科学研究科教授
山口 栄一 氏
京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科教授・美術工芸資料館長
並木 誠士 氏
染色作家
森口 邦彦 氏
釜師 大西家十六代当主
大西 清右衛門彦 氏
長谷川 和子(京都クオリア研究所)

お話をうかがっていると、京都というのは伝統と革新の連続だと、私たち、よく言うんですが、どうも琳派のキーワードって「自由」っていうことなのかなあ、なんて思いに至りました。 森口さんのデザインが採用されこの4月にデビューする三越のショッピングバッグであれ、大西さんの、たたらの技術を使ったアートであれ、その自由さみたいなものを、もう一度、私たちの中でかみしめてみることが必要なんじゃないかと感じました。
この後、山口さんにファシリテーターになっていただき、討論をお願いしたい思います。
山口 栄一(同志社大学大学院総合政策科学研究科教授)

きょうのテーマの世界に関しましては、私が一番門外漢だと思いますので、まず私から質問させていただきます。
最初に、並木さんにおうかがいたします。 お話を聞いて、あっ、なるほど、と思ったのは、琳派というのは、突然現れたある種のブレークスルーだったということです。 つまり、今まで「絵」だった世界が、突然「デザイン」になった。 昔、南フランスに3年間住んでいた時に、私は1週間に1回ぐらいの割合で、娘や息子を連れてアンティーブのグリマルディ城のピカソ美術館に行っていました。 そこには晩年のピカソが飾ってありました。 もう完全に、キュービズムのさらに先に行ってしまったピカソの作品。 ヴァロリス焼の陶器が並んでいて、それらは、圧倒的な「突き抜け」感を感じたものです。
実は、400年前に日本でも、絵から始まって、造形の世界にブレークスルーがあったんだ、ということを今日は学ぶことができて、驚きでした。 これは、何がきっかけで生まれたのでしょうか。 徐々にこういうものが生まれたのか、突然生まれたのか。 そして、こういうブレークスルーが生まれたのは、何か時代背景があったのでしょうか。
並木 誠士(京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科教授 美術工芸資料館長)

なかなか難しいんですけれども、今、たまたまピカソの話が出たんで、また、先ほどからのみなさんのお話を加えていうと、琳派の人たちというのは絵だけではないんですね。 着物の柄の制作を最初からやっている。 ピカソも、陶器を作ったり色々してますけれども、実際に琳派の画家たち、っていうか、まあ、デザイナーと言ってもいいと思いますが、この人たちがデザインした蒔絵があり、何がありというところがあるので、宗達の下絵なんかもそうですけれども、いわゆる、狩野派のような、襖や掛け軸に絵を描くだけではなくて、そういう、いろんなことをやる下地があったということ事態が、ブレークスルーの一つの大きな出発点になったと思うんです。
ご存じの方も多いと思いますが、俵屋宗達っていうのは、江戸時代の小説に、「扇は都の俵屋」というのがあって、扇で有名な俵屋というのは宗達の屋号だと一般に言われてるんですけども、扇というのも、閉じたり開いたりで形が変わるわけですよね。 また、きょうは尾形光琳の「燕子花」の屏風なんかも、フラットな画像でしかお見せできませんんでしたけれども、屏風として置くと、それが既に立体になっているっていうことがあって、そのあたりのことを宗達、光琳はかなり意識的に考えている。 なので、絵という概念が平面だという発想は、端からなかったんじゃないかと思うんですね。 これが、きょうのテーマにも通じる、三次元性、つまり立体と平面の関係みたいなことに出て来ると思うんですけれども。 そこが、他の画家たちと違って、他の画家はやっぱり襖の平面になんとか3次元を描くという事をしてたんですけれども、宗達たちの作り方というのは、そもそも平面だけを意識していなかったというところがある。 さっきの森口さんの着物の幾何学模様が、着られた時にどう見えるかというお話も含めて、やっぱり平面だけでは考えない発想っていうのが、一つの新しさを生み出す原因だったんじゃないかという気はしていますね。
山口
はあ、なるほど。 しかし400年前の日本では、今流の芸術家ではなくて、あくまでクライアントがいて、その要求に応じて職人として作るわけですよね。 そうすると、クライアントも相当自由でなくちゃ頼めないわけじゃないですか。 その辺はどんな具合になっていたんでしょうか。
並木
そうですね、そのあたり、一つの大きなポイントを握るのが本阿弥光悦という人だったと思うんですけども…。 光悦は、さっき「鶴の下絵」に和歌を書いていましたように、もちろん古典的な教養がすごくある人なんですけれども、元々、本阿弥家は刀の研ぎをやっていた家ですし、それから、光悦の字というのは、やっぱり、それまでの藤原定家以来のきちっとした字の崩し方ではなく、非常に自由な字の崩し方をしているというところがありますし、光悦の周りに宗達とかもいたので、そこでやっぱり、今風にそれらしくいうと、かなり「自由なものづくり」ということを感じ取ることができたんじゃないかと思うんです。 それでいうと、光悦が、1615年に屋敷をもらったというのは、一つの琳派のきっかけとしてもいいんじゃないかと思いますね。
とにかく、光悦の存在はすごく大きかったし、明治時代なんかは、宗達よりも光悦が非常に評価されていて、「光悦 光琳派」なんていういわれ方をしたぐらいですから、それも含めて考えても、光悦の存在っていうのは、きょうはあまり話をしませんでしたけども、琳派にとって、ものづくりの一つの原点だったんじゃないかという感じがあります。
山口
有難うございました。 では、森口さんにうかがいます。 森口さんは、ほとんど毎回AGORAに来てくださって、気軽に「森口さん」て呼びかけてしまうのですけども、「人間国宝」でいらっしゃる。 人間国宝だと思うと、喋るのは少し恐ろしいのですけれども、きょうは初めて、森口さんが、今日の染色作家となる最初のきっかけを教えてくださって、そこが心に刺さりました。 フランスに行って、もうフランスから帰るまいと思っていらっしゃった。 そこで、師匠に「お前は帰れ」と言われ、日本に帰ってくる。 日本に帰ってきて弟子たちに教えられながら、何かブレークスルーしなければならないと追い詰められた。 そして、その中で作品を一つ作った。 それがブレークスルーにつながったわけですね。 私は、きっとその中にはフランスで得たさまざまな回遊体験があったんだろうと思います。 それがどんなことだったのか、なぜブレークスルーできたかということを思い起こして語っていただけないでしょうか。
森口 邦彦(染色作家)

あの、それ、ちょうど言おうと思ってたんですよ。 空間的なことばかり、つまり、外国のことばかり考えてたらダメなんですね。 大事なのは、「複文化」を自分の中に持つっていうことで、一元的な文化の中でしか生きていけん人間となぜ、ぼくがフランスに行ったかというのが、根源的な問題ですね。 ぼくは、1959年に京都市立美術大学に入ったんですが、当時は、ジャクソン・ポロックとかラウシェンバーグとか、アメリカンポップスが大流行でですね、日本でいうと、山口長男、齊藤義重のような抽象美術が華やかなりし頃で、学校でもそういうものをものを真似したり、具体美術の作家が学校に講演に来られて、白髪さんなんかが、天井からロープで体を吊って、床に置いたキャンバスに絵の具を散らしながら、足で絵を描かれたり、あるいは、イヴ・クラインみたいに、キャンバスを立てて、その前に女の人を立たせてスプレーで人体を表現するなど、そういう描く行為そのものを、真似をしていたわけです。 ぼくたちの先生というのは、上村松篁先生とか、猪原大華先生や秋野不矩先生という錚々たる人たちで、そういう方が毎日教えに来られていたのですけれども、そういう先生たちに反抗するようにアメリカンポップスにのめり込むような風潮だったんです。 でも、実はぼくは、友だちがのめりこめばのめりこむほど、なんかあんまり好きではないなと思うようになったんですね。
それでフランスだったんです。 ちょうどそんなころ、「ルーブルを中心とするフランス美術展」というのがありまして、その中には、近代のものもあって、さっきのバルテュスの作品もあったようなんですが、とにかく、そこでヨーロッパ・フランスとの出会いがあった。 あ、ぼくはアメリカじゃないなと思ったんです。 それをきっかけに、関西日仏学館に通いフランス語を教わり、そこで、フランス政府からお金をもらって留学できるっていうことを知リまして、必死で勉強したんです。 先程も申しましたが、うちの父は、非常に自由で闊達な作品を作っていたにもかかわらず、単なる職人さんで、なんでマチスやピカソのように、社会的に認められないんだろう、とぼくは、常々、日本というものに多いに不満を持っていたんです。 それで、ぼくはこんな国は嫌やというふうに思ってですね、もっと、自分が認められる国に行きたいというのが、一つ。 それから、美大では、歴史に名を残されるような先生方にご指導願ったんですけれども、ぼくの中に湧き出る、何っていうか、ふつふつとする「創りたい」という気持ちには沿ってもらえず、なんか抑えつけられたまま抵抗できずの過ごしてしまい、今から思えば、もったいないことをしたなあと思いますが…。 それで、フランスの学校に行くと、そうではなかった。 普通の留学生という立場だったら、研修生―stagiaireということなんですが、友達の進言で一般学生に登録しまして、その授業を受けました。 その中で、スイス人のデザインの先生方が、私の感性とすごく合う人たちだったと思うんですね。 彼らは、ぼくの創造性をものすごくくすぐってですね、「もっと遠慮しないで自分自身を見つめなさい」みたいなことを教えてくれた。 こうしたことが、ブレークスルーと言われるものにつながったんだと思いますね。
山口
友禅の世界で、「デザイン」によって友禅を染め付け、ある意味でパラダイムを壊したわけだと思うんですけれども、いろんな反発とかあったのではないかと想像します。 いかがだったでしょう。
森口
そうですね、ぼく自身は、もう、それでしかありえないものを求めたんだけれど、結果として父とも違った、友禅の歴史の中ではかなり異質なものを提案してきたわけです。 ですから、ぼく自身が人間国宝と呼ばれる立場であることのほうが逆におかしいかもしれませんね。 でも海外からは評価してもらえてるようです。 どうなってるのかなと思っています、今でも。
山口
有難うございます。 最後に大西さんにおうかがしたいのですけれども、先ほど1600度で溶かしているとおっしゃっていましたから、炭素含有量が殆どないですよね。 鋼に近いですか。
大西 清右衛門(釜師 大西家十六代当主)

鋳鉄は、炭素量が4.3%から現在の鋳鉄は2.5%。 ただし、私どもの400~500年前のものは、ほとんど結晶状態が違ってですね、4.3%ぐらいの鋳鉄ですね。 鉄には5元素がありまして、マンガン、燐、硫黄そして炭素、シリコン。 それで、流してやるということをしなきゃいけないので、炭素量が必要になる、もしくは、現在ではケイ素を足して流れやすくしています。 そういうものが、昔はアンバランスだったんです。
山口
ヨーロッパで、鋳鉄―キャスティングの技術がきちんと成立したのは1540年ころだと思うんですよね。 中国、日本には「たたら」の技術があり、相当古いと思います。 ヨーロッパでは、450年ぐらい前にやっと生まれた。 しかも、炭素含有量が無茶苦茶多いですから、いいものはあまりできなかったと思うんです。 ということは、鉄でもって造形をするという世界が生まれたのは東アジアで、とりわけ日本だと思うんです。 ですから、これって、ぼくたちすごく誇るべきもので、釜のような鉄による造形というのは、日本のオリジナルと言えると思うんですが、どうでしょう。
大西
フランスでは、chaudron(ショドゥロン)というのがあるんですね。 caldron(コールドゥロン)というのがイギリスにあります。 鉄というは、中世の時期、同時にいろんなところで栄えるんです。 ところが、火事に弱いとか、特に、やはり、錆に弱いわけなんですよね。 ところが面白いのは、日本の鉄っていうのは、300年ほど前のものですが、金槌で割ったら、銀色の鉄が出てきます。 まだ生きているんです。 これは表面からじわじわと錆びていって、まあ、形がなくなっていくわけなんですけれども、実は、この素材でエンジンを作ったらいっぺんエンジンをかけるだけで割れてしまいます。 大変さくい。
そして、炭素分が金属炭素として析出されます。 だから、これ、ドリルで穴をあけられないですね。 今の鉄は、なんでドリルで穴があけられるかというと、黒鉛が入っている。 このため柔らかい部分になって、穴もあけられ、振動も吸収するとか油を染み込ませて錆びないようにするなど、現代の鉄はいろいろな用途に使えるようになっている。 一方、この昔の鉄は、水が染み込まないです。 だから500年も使えるんです。 これで、私ら、ちょっと困るんですけどもね。 まあ、底の部分は熱疲労を起こしますけれども、その部分は割って、新しく底を作って、漆と鉄具の接着剤でくっつけ、使いつづけることができるわけです。
山口
ということは、工業用に作られた鉄とは違うんだ、と。
大西
と言うよりも、アフリカで作った鉄も、中国で作った鉄も、アジアの端で作られた鉄も、最初は、燃料が木炭から始まり、そして鉄鉱石、もしくは砂鉄っていうもの、もしくは鉄がリサイクルされると、ほとんど同様の鉄になってしまいます。
高田 公理(佛教大学社会学部教授)

鉄もさることながら、ヨーロッパに比べると磁器も、日本は早くに手がけていますね。 ヨーロッパで磁器が焼けるようになるのは18世紀。 むろん日本だけではなくて、中国はじめ、ヨーロッパに比べて東アジアの方が進んでいたわけです。
ところで、琳派のことを考えるために年表を作ってみたのですが、光悦村ができるのが1615年。 で、千利休が没する時に、本阿弥光悦は30歳前後なんですね。 今日の話し手のおひとりである大西さんは、茶の湯の世界からいらしているわけですが、並木さん、茶の湯と琳派の間には相互に、どんな関係があったのか。 教えていただけますか。
並木
あのう、時期的には、まあ、そうなんですけれども、意外と、と言うか、あまり直接関係ない。 むしろ、意外なくらいない。 もちろん、当時の教養としてあったわけだし、光悦を中心とする人たちは、当然、お茶も〇〇もやったっていいますし、そういう点では関わりはあるんでしょうけれども、造形面で、どういう形でお茶と琳派が関わっているかといわれると、意外と少ないんですね、そういう考え方はね。 もっとあって、私たちが知らないだけかも知らないですが、琳派の造形とお茶が直接結びつくかっていうとそうではないと思います。
高田
なるほど、そうですか。
ところで、茶の湯は、一種の室内芸能なのですが、それは当時の富裕な階層を中心にして、生活スタイルそのものを変えていくような大きな力を発揮したわけでしょ? そこで琳派に目を向けると、彼らが創出した造形も、単なる造形にとどまらなかったのではないかという気がします。 実際、光悦村は、ある種「Life Museum」みたいなものだったという印象を受けるのですが……。
というのも昔、梅棹忠夫さんが「国立民族学博物館」を作ろうとしておられたときに、「これはねえ、現代の光悦村なんや。 ぼくはそういうものを目指しているんや」とおっしゃっていたのが、とても強い印象と共に記憶に残っているんです。 光悦村そのものについて、ぼくは余り何も知らなかったのですが、そんな梅棹さんの話を耳にして、琳派というのは、単なる造形の問題なのではなくて、いわば人間の生き方というか、暮らし方のスタイルそのものを追求したのかなあ、などと思わされたものです。
そこで琳派と同時代のヨーロッパの造形を見てみると、ちょうど当時は、遠近法を用いた写実的な絵画が本格的に成立する時代だといっていいのではないでしょうか。
つまり、それよりは少し前ですが、ルネサンス以前のヨーロッパ絵画は、キリスト教というか、聖書の物語を視覚化した、まるでリアリティのない絵を描いていたわけでしょ? それがボッティチェルリの「プリマベラ(春)」あたりを画期に、着実に写実的な絵画に近づいてくる。
やがて16世紀になると、それ以前にダ・ヴィンチが発明したということになっているカメラ・オブスキュラ――外界の投影図を見ることのできる、いわば巨大なピンホールカメラの中に入って遠近法を身につけ、それに基づいた外界の写実的な絵を描く絵描きが輩出するんですね。
このあたりを境に、ヨーロッパでは、まるで写真であるかのような写実的な絵画が描かれるようになります。 ところが19世紀後半、印象派の登場で、そうした写実性が相対化され、さらに20世紀に入ると、キュービズム(立体派)のピカソをはじめ、逆に非常に抽象度の高い絵画表現が発達するわけです。
そこで琳派に目をやると、ちょうどヨーロッパの絵画が、写実性を高めた時代に彼らは、ある種の抽象絵画というか……立体感に満ちた空間性のようなものを全部そぎ落とした造形世界を構築していったような気がするのですが……。 あ、これ「抽象」というよりは、写実的な空間性の「捨象」だと考えるほうがいいのかもしれませんね。
しかし、抽象なのか捨象なのかは別に、ヨーロッパで抽象絵画が登場する300年ぐらい昔に、写実性からの離脱を試みたというのは、非常に面白いなあと思わされました。
そういう風に考えて森口さんの作品を見せてもらいながら、お話をうかがうと、「なるほど、琳派との接続性がありそうや」という気がしてくるわけです。
ついでに申し上げておきますと、森口さんは、「その境地に至るには、徹底した写実の訓練が必要なんだ」とおっしゃっていましたが、キュービズムの創始者といっていいピカソの写実的描写力もすごいですよね。 そんなことを考えると、400年前と現在のヨーロッパと日本が、ときにまるで異なった方向を目指しつつ、相互に共鳴する要素を育ててきたことが、よくわかるような気がするのですが、並木さん、いかがでしょうか。
並木
なかなかダイナミックで、あのう、私の観点とは違うので、ちょっと、私の考えを述べて、より話を進めていきたいと思うんですけども…。 琳派って、私がすごく面白いと思うのは、抽象との結びつきっていうよりも、やっぱり今のデザイン的なものに対する近さだとおもうんですけども…。 大袈裟ですけども、世界中の絵画を見ると、いくつかの大きな転換がある。 一つは、抽象絵画の登場ですね。 「アヴィニヨンの娘たち」をピカソが描いて、1907年なんですけども、キュビズム、抽象画が出てくる。 それまで、りんごを描くとか、犬を描くとかっていうのが絵だったものが、何かそういう具象ではないというものを描くようになってくるというのが大きな変化だった。 ただ、年代的にいうと、もっと大きな変化が昔起こったのが何かというと、水墨画なんですね。 水墨画というのは、本来、赤いリンゴとか黄色い花とかあるものを、全部、墨の濃淡だけで表そうという風に考えるわけですね。 これはもう、絵画が本来、目の前のものをできるかぎり忠実に再現したいという欲求から生まれてきたにもかかわらず、突然、7世紀、8世紀の中国で、墨の濃淡ですべてを表現しようということが起こって来る。 これは、もしかしたら、抽象絵画の登場より衝撃的な話かもしれない。
では、日本では、何が一番衝撃的な絵画の転換点かというと、それは、宗達のさっきの作品とかだと思うんですね。 で、それは抽象とかそういう問題とは、ちょっと違う問題ですけども、絵画が大きく変わったということを考える時に、やはり、抽象絵画のピカソの代表的な作品による転換点ということと、水墨画の成立ということを考える時、若干スケールの差はあるにしても、やっぱり、宗達が登場して、ああいう、それこそ300年ぐらい後のデザインに通じるようなものを創ったというのは、絵画の歴史の中では非常に大きな飛躍であったと思うので、それは、琳派で一番評価できる点じゃないかと思うんですけどもね。
高田
多分、そのことと関連するのでしょうが、家の紋章ですね。 ヨーロッパでは、やたらゴテゴテしたデザインのが多い。 それに対して、近世の日本で成立した紋章は、きわめてシンプルで訴求力が強い。 そういう意味で、早期近代のヨーロッパと日本とは、造形性に関して非常に対照的だったよう気がするのですが……。
並木
日本の文様は、最初、中国からいろんなものが入ってくるんですが、例えば、中国には、饕(とう)餮(てつ)文(もん)のようにやたらに埋め尽くす、銅器の周りを埋め尽くすような文様がある。 そういうものが入ってきて、正倉院の宝物なんかはやはり、もの全体を何か模様で埋め尽くさないと気がすまないみたいなところがあるんですけれども、だんだんそれが、シンプルになってくるし、あのう、「片身替わり」のように、半分で分けて、図柄を替えてしまうみたいな感じで、埋め尽くさないで、そこに、陳腐な言葉ですが、間とか、わびとかが出て来る。 大きな流れでいえば、日本の特徴、つまり文様が日本化して行くという特異な流れがあったと思うんですね。 これが、平安時代の後半ぐらいから出てきて、蒔絵なんかでも全体を埋め尽くすようなものから、少し間があったりなどするということが見られるわけです。 日本の中で、何か、ある種のシンプル化に向かう方向というのがあったと思うので、そういう意味では、文様自体も中国的なデコラティブで空間充填性の高いものから間のあるものに向かうという流れの中で、先ほどおっしゃった、非常にシンプルな紋章も生まれてくるということがあったのかもしれない。 漢字からひらがなを作っていくという方向も、一つのシンプル化の流れだと思うんですけれども、紋章もそういう流れの中にあったんじゃないでしょうか。

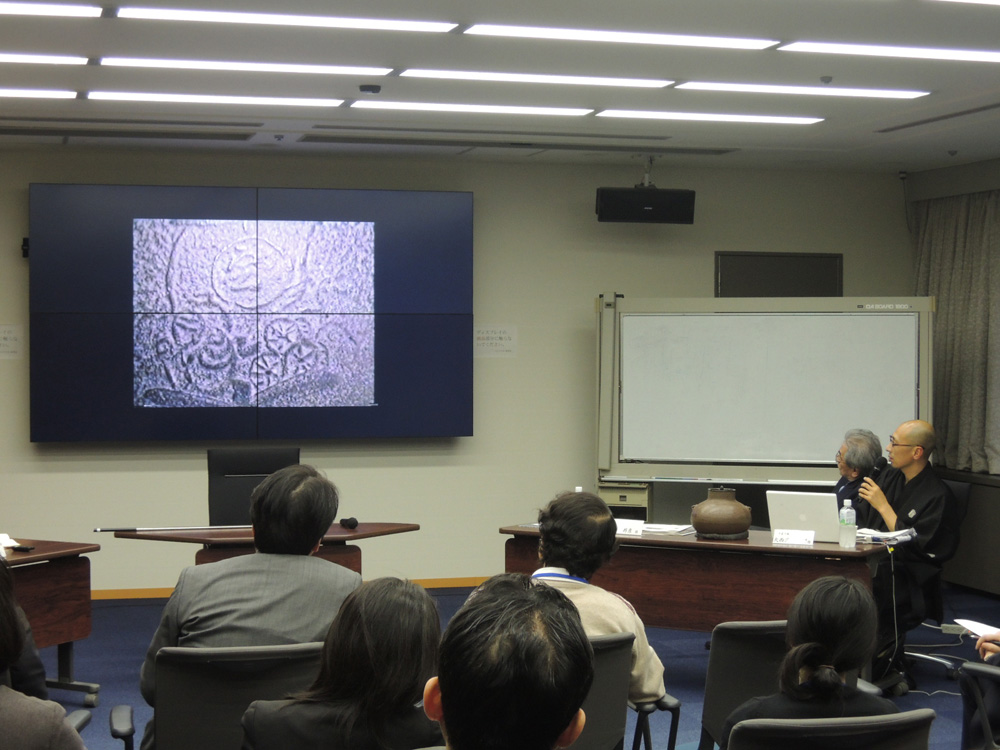
山口
ここらで、会場からどなたか質問はありませんか。
村瀬 雅俊(京都大学基礎物理学研究所准教授)

大西さんにおうかがいしたいのですが、400年前のものを復元するのに20年もかかったとおっしゃったんですが、できあがったものから、でき上がるプロセスを考察するというのは、具体的にはどんな試行錯誤があったのかおうかがいしたいと思います。
大西
ぼくとこはまあ、400年続いているわけですけども、先祖がしているのにできないわけなんですね。 そこに、ものすごく、心理的にそれでいいのか、と思いがあった。 それで、復元をやってみようとするが、教えてくれる人はいないわけです。 そんならということで、彫刻一つできない20代の頃に、ものから痕跡をみいだすということをやり始めたんです。 先祖のかなり複雑な技法の解明を、一つずつ実験をやって試していきました。 それで18年かかり、その後にチャレンジして20年で、やっとうまくいった、ということなんです。 その時、昔の作品と私の復元作品の痕跡が同じように合体できたので、350年前の技法が復元できたと考えたわけです。
とにかく、すべてにおいてわからないことばかりです。 技法はいっぱいあるんですね。 デザインに関しても、最初は、お湯を沸かすのに何がデザインで変わるの、と、分からなかった。 例えば、つぶつぶでも、それを揃えるの何が面白いのか。 不思議やったですね。 父親は、工房に、私を全然入れてくれなかったので、高校時代から勝手に工房に入りだしてそういうことを見ていって、装飾というものが持つ面白さもわかってきました。 一つは、〇〇○おろし金というのがあるんですよ。 山芋なんかをおろすのに、木の板に鉄の固まりないし石を詰め込んでおろし金にしている。 ただ、おろし金の機能だったら均一に並べるだけでできるのに、文様にしているようなことなんですね。 ていうところで、デザインというものは、日常に使うものにも含めていったら面白いと感じるようになったんです。
それで、琳派のことなんですが、野々村仁清は仁和寺で仕事をさしてもらっていたんですね。 だから、「仁清」が名乗れた。 作家の始まりといわれますが、壺に絵柄を入れていくことででも、仁和寺の許可がなかったらできないし、外にも自由には出ていけないんですね。 この時代に、琳派の人もそんなに自由な発想が持てたのかな、と思うんですよ。 英一蝶は、お妾さんの絵を描いて島流しに会うわけです。 そんな時代ですから、実は、施主の要望に応えるという制限の中で、自由な発想をし認められているというようなことで、今のような何もかも自由というのとは違うと思うんです。 ですから、琳派の時代というのが一般に言われているような芸術の自由というのがあったかどうか、疑問に思うんです。
山口
他にいかがでしょうか。 では、お題に近づいていきたいと思います。 今、実はですね、デザインスクールというか、デザインというのが一つの世界的潮流になっていまして、ここASTEMにも、「京都デザインスクール」っていうのがありますが、多分モデルにしたのはスタンフォードだと思います。 スタンフォードの中にデザインスクールがあって、これ、要するにみんなが寄り集まる仕組みなんですね。 特に、メディカルスクールの中にバイオデザインというのがあって、今、それがすごくもてはやされています。 その中には、医者がいたり、技術者がいたり、マーケティングの人がいたりして、で、医者がこんなもの作れないだろうかというと、みんながワイワイガヤガヤやって、新しい製品を作る。 薬は作りません。 造形だけするんです。 そういうのが流行っていて、今、日本でも日本版バイオデザインを作ろうなんて言っているわけです。
それで、今日のお話を聞いて、私、目からうろこでしたけども、私は、スタンフォードのデザインスクールやバイオデザインに何度もいって、大したもんだと思っていたんです。 しかし、なんのことはなくて、日本には、そんなデザインスクールはとっくに京都で光悦村としてあったわけなんですね。 しかも、京都の地には、こんなにも濃密な、いわば中心性を持った人々がいて、森口さんのような人間国宝がいたり、大西さんのような釜師がいたりして、いわば完全なオリジナルな形でそういうものが京都にあるわけです。 だから、何もアメリカ、スタンフォードから借りてこなくても、私たちの知恵でもってデザインスクールってのはできる。 デザインスクールで基本的に何をやっているかというと、未来のビジネスを考えようとしているわけです。
それで、少し話を飛んで、もちろん、この芸術あるいは工芸の世界、造形の世界というのはものすごくあるんですけども、それに基づいて、私たちの世界でこのデザインスクールをつくってみようか、というのは一つの話題としてあると思います。 高田さんのコメントをうかがいながら少しずつ形にしていきたいと思います。
高田
「デザイン design」という言葉の「de-」の部分は「外に向けて出す」、そして「sign」は「しるし」ということですね。 ですから「デザイン」は「単に形を造る」こととは全然違う。 だからこそ、単なる「造形」とは異なる「意匠」という日本語があるわけです。
そこで、同じヨーロッパでも、イタリアとデザインを比べると、かなり考え方に違いがあります。 たとえばフランス人は、非常に外連味の強い造形が得意です。 それに対してイタリア人が何かを作るときには、まず素材研究から始める。 つまり、家具の場合なら、素材が金属であるか木であるか、それともプラスチックであるかによって、造形に大きな違いが出てくるはずだと考えるのです。 結果、イタリアの家具などは暮らしにしっくりと馴染みやすい。 その点でフランスの外連味に満ちた造形物は、必ずしも暮らしに馴染みやすいかどうか、むつかしい問題が残るようです。
こう考えてみると、何かをデザインするとき、造形だけを考えるのでは、うまく行かない場合が出てくる可能性がある。 だから、住宅でも家具でも衣服でも、造形の専門家は不可欠ですが、その周辺に、それ以外の多様な能力を持った人がいて、協力してもらえる条件が不可欠なのだという気がします。
こういう話になると、つい、いつも同じことを言ってしまうのですが、そうした多様な資質を身につけた人々が自由に出会える、本格的なユニバーシティが、京都には皆無、なですね。 かりにも「ユニバーシティ」を名乗るには、理科系と文化系だけではなくて、芸術・芸能系、スポーツ系などがワンセット、揃っている必要があります。
そこで、たとえば京都大学の英語名を見ると、これが「Kyoto University」なんです。 本来、というか、本格的なユニバーシティなら「The University Of Kyoto」を名乗るべきところを、なにを遠慮したのか、「Kyoto University」を自称している。
これに比べると東京大学の英語名は「The University Of Tokyo」なんですね。 でも、東大にも体育系、芸術系などはありませんから、ユニバーシティを名乗るのは、おこがましい。 そこで京都という街を見直してみる。 すると、その街全体は、あらゆる専門性をはらんだ知的・芸術的・技術的ストックを体現しているといっていい。 ならば、京都の街全体を「The University of Kyoto」なのだと考えればいいのではないでしょうか。
そうすると、山口さんがおっしゃっていた、包括的な意味でのデザインのできる都市、というか巨大な大学ができるのではないですか。 まあ京都は、オックスフォードやケンブリッジよりはかなり大きいかもしれませんが、規模としても適切だと思います。 その際、既存の大学だけでなく、企業をはじめ、創造的な仕事をしている人の集まりは皆、一種のインスティテュートだと考えるべきでしょうね。
すでに京都では、いわゆる「コンソーシアム・京都」が始動していますが、まだまだ全体としての統合性には弱さがある。 それを基礎に、きちんとした「ユニバーシティ構想」を打ち出したいものだと思います。
山口
私、今度の京大のリーディング大学院はデザイン系の大学院って聞いたんですが、多分、きょう出ていたような発想はないですよ。 多分、やっぱりスタンフォードの受け売り、コピーという感じでいると思います。 立命館も確かデザインセンターというものを作りました。 これも、スタンフォードのデザインスクールの流れを組んでるんですね。 そうじゃないんです。 ここにはせっかく人間国宝がいますから、京都から作る全くオリジナルなデザインスクールってどんなものになるだろうというのを、きょうのワールドカフェのお題にしたいと思います。 まあ、そんな難しいことより、並木さん、森口さん、大西さんが一堂に会してくれた希有の機会ですから、ワイガヤで会話をみんなで楽しみ、最後に、デザインスクールのいいアイデアが出ればというぐらいの気持ちでやったらどうかと思います。 では、最後に、並木さんみなさんのお話を聞かれて、感想を一言聞かせていただけますか。
並木
琳派の話は、きっかけだと思うんですね。 妙な幻想を抱くことはないと思うんです。 「琳派400年」とかって言いだすと、何か、琳派をすごい目標値のように考えるきらいがないでもないと思うんですけども、むしろ、まさに、今のお話でもあったように、日常の中で何を見つけるかということであって、面白さとか、使いやすさとかいろんなことを考えるのがデザインだと思うので、そこに琳派もあったというふうなことであり、あまり祭り上げないほうがいいんじゃないかと思うんです。




