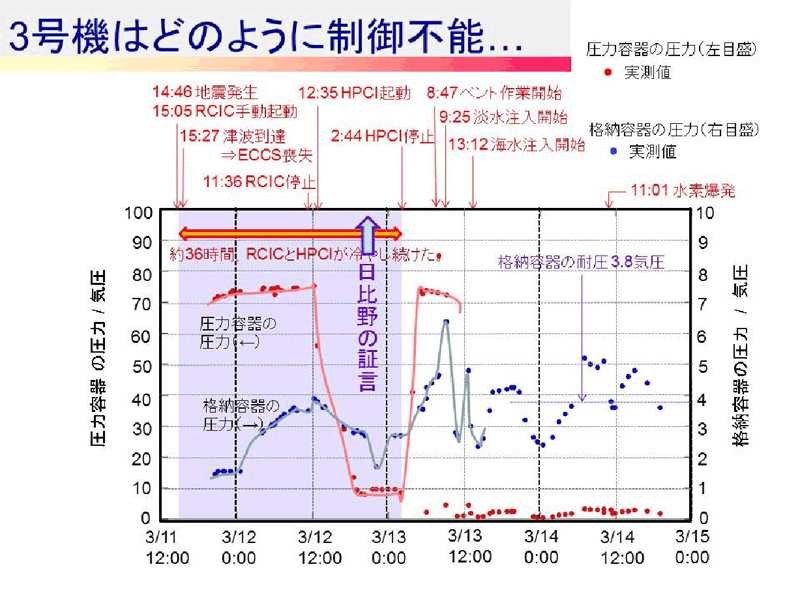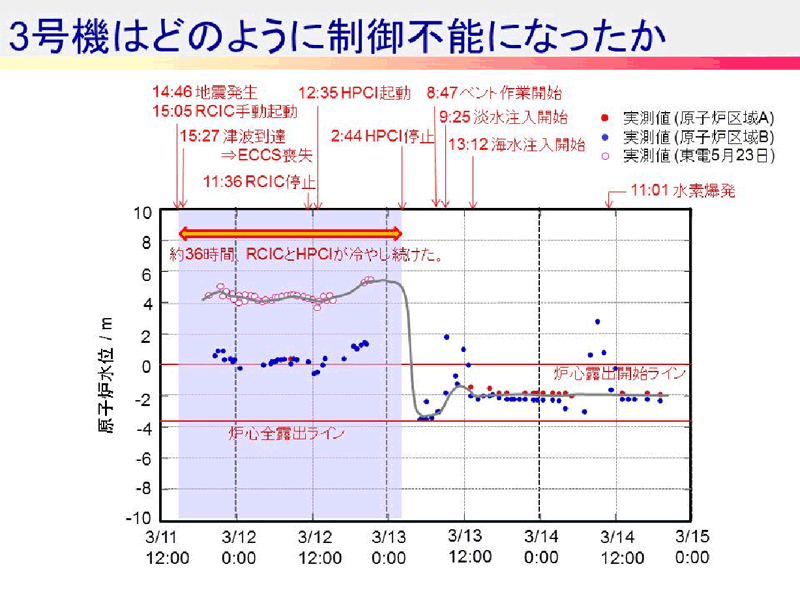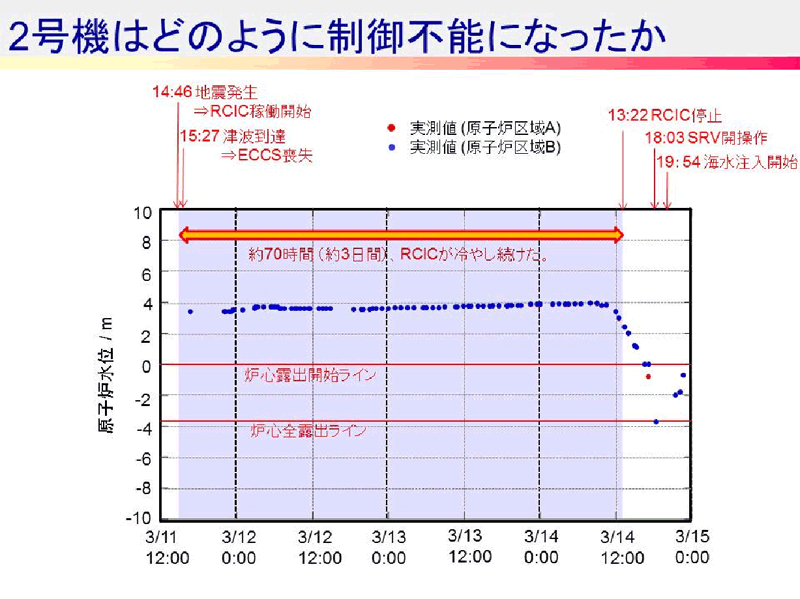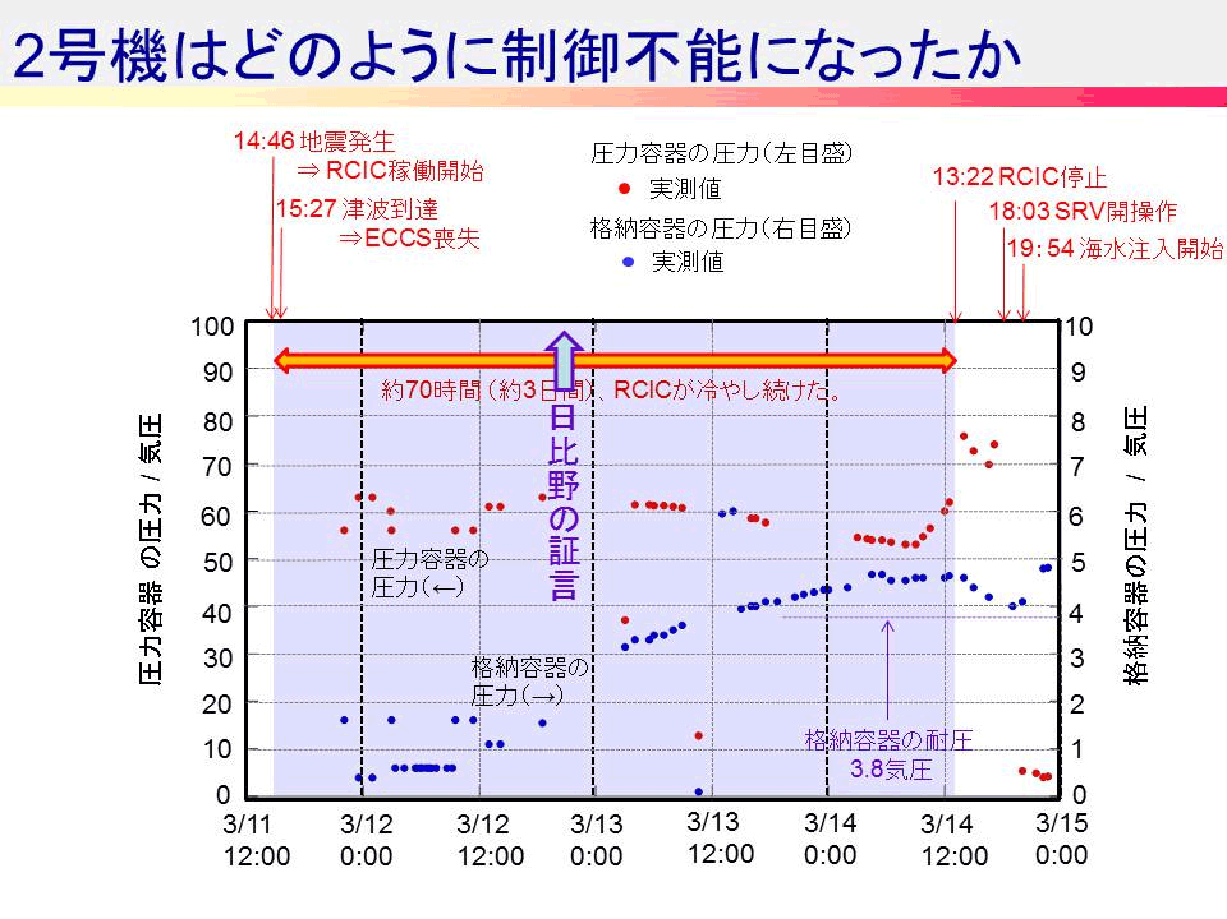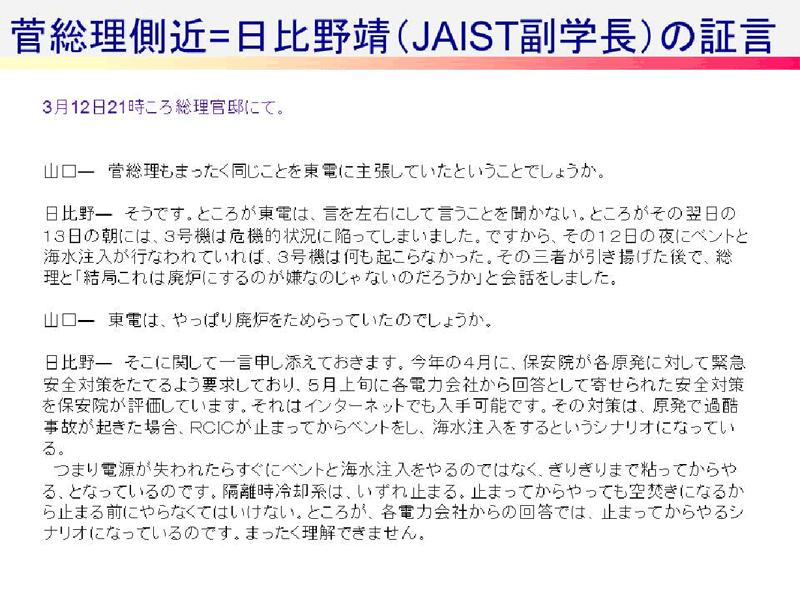活動報告/クオリア京都
第1回クオリアAGORA/~福島原発事故は何故起きたのか~
まず山口栄一(同志社大学ITEC副センター長 同志社大学大学院総合政策科学研究科教授)がスピーチ、これを受けて堀場雅夫(堀場製作所最高顧問) 篠原総一(同志社大学大学院経済研究科教授) 高田公理(佛教大学社会学部教授) 山極寿一(京都大学大学院理学研究科教授)がディスカッション、最後はスピーカー、ディスカッサントとともにワールドカフェを開催しました。
経営者や企業などの幹部、研究者ら約40名が侃侃諤諤、私たちが遭遇したFUKUSHIMA問題について意見交換しました。
≪こちらのリンクよりプログラムごとのページへ移動できます≫

第1回クオリアAGORA/~福島原発事故は何故起きたのか-技術経営の底知れぬ愚かさ~/日時:平成24年5月31日(木)16:30~20:00/場所:京都高度技術研究所10F/スピーカー:山口栄一(同志社大学ITEC副センター長・総合政策科学研究科教授)/【スピーチの概要】 津波のあと非常用電源がこわれ、ECCSが稼働しなくなったものの、「最後の砦」たる非常用復水器(IC)と隔離時冷却系(RCIC)は、それぞれ1号機および2・3号機で稼働しました。 これら「最後の砦」が動いている問は、原子炉は「制御可能」でしたから、その間に「ベント&海水注入」をしていれば、原子炉の暴走は起きませんでした。 しかも、「制御可能」時のベントは放射陛物質をほとんど出しません。 しかしながら、東京電力の経営者は、海水注入を拒み続けました。 この故意による拒否を疑義なく論証します。 この論証によって、この事故の本質が「技術」ではな<、「技術経営」にあること、そのため東電の経営者の刑事責任はきわめて重いことを明らかにします。 /【略歴】1955年、福岡県生まれ。 79年、東京大学大学院理学系研究科物理学専、攻修士課程修了。 同年、日本電信電話公社に入社。 米国University of NotreDame客員研究員、NTT基礎研究所主幹研究員、仏国IMRA Europe招聘研究員、経団連21世紀政策研究所研究主幹などを経て、2003年より現職。 2008年にはケンブリッジ大学クレア・ホール客員フエローとして英国ケンブリッジに在住。 ベンチャー企業の (株)アークゾーン、(株)パウデック、ALGAN(株)、Connexx(株)を創業し、各社の取締役を務める/WORLDCAFE―クオリアAGORAはワールドカフェスタイルにて開催されます。
※各表示画像はクリックすると拡大表示します。
問題提起スピーチ

同志社大学大学院 総合政策科学研究科教授 山口 栄一氏
クオリアAGORAでは、常にホットな話題をテーマにと考えていますので、まず第1回は、国会の事故調査委員会も開かれたばかりの福島原発について、私がディスカッションへの問題提起をすることになりました。 お手元の資料は、みなさんが初めて目にするデータばかりと思います。
まず、福島原発の1号機と2、3号機の配管構造の図を見てください。 原子炉の炉心(燃料棒)は、「やかん」と思ってください。 原子炉の問題は、科学でもなんでもない。 技術です。 そして、その技術とは、要はこのやかんをいかに冷やすかという問題なのです。
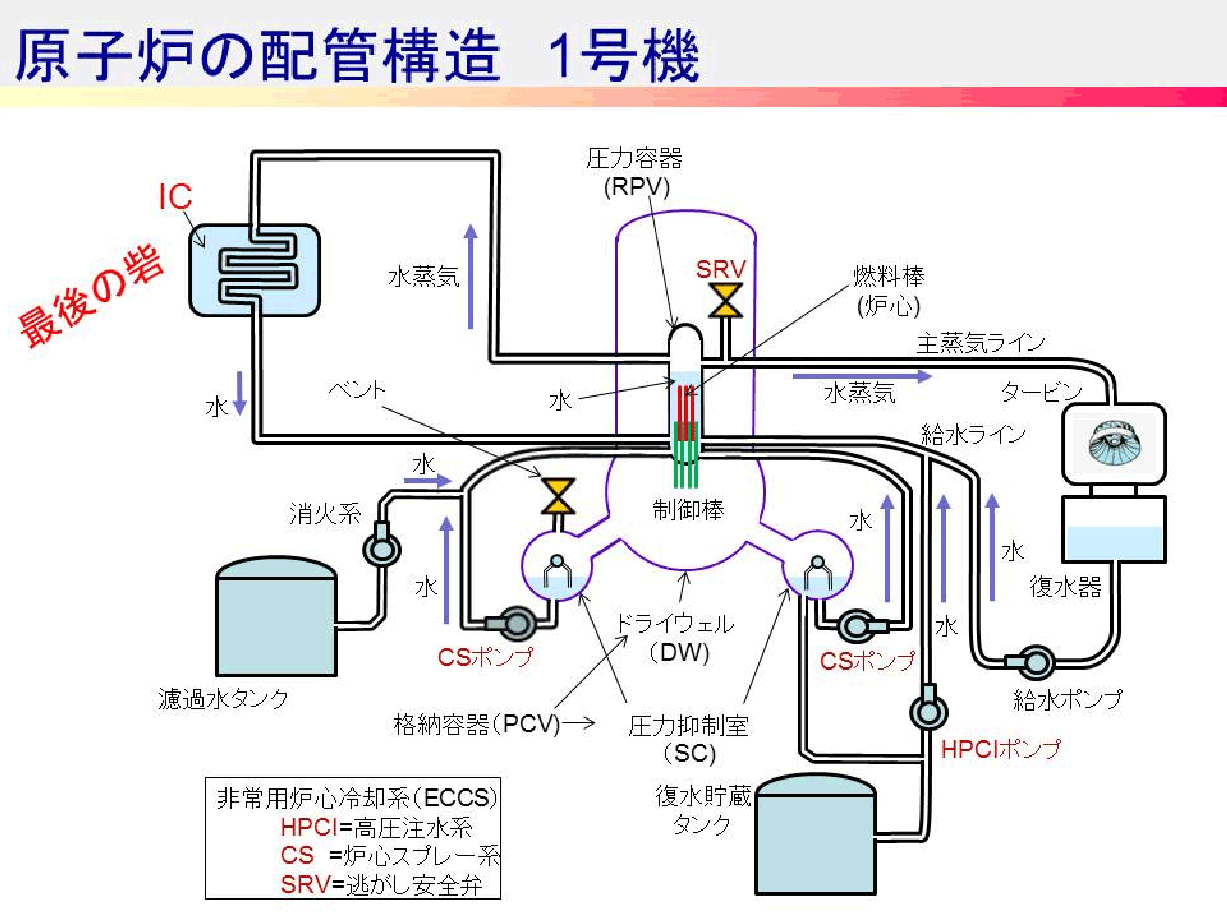
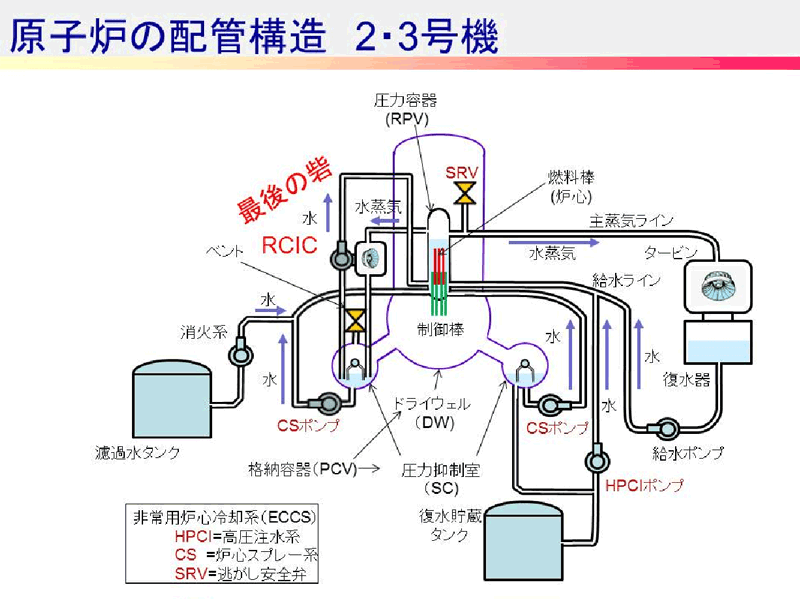
原子炉の構造を見ていきましょう。
炉心で作られた水蒸気は、この主蒸気ラインを通り、タービンを回して電気を起こします。 その後、蒸気は復水器で、大量の海水によって冷却されて水にもどされ、それがまた炉心に戻って炉を冷やします。 ところが、津波のあとAC電源が壊れ海水を取り込むポンプが壊れて、この主蒸気ラインを通じての炉心の冷却ができなくなりました。
しかしこの事態になった時でも、非常用炉心冷却系(ECCS)というシステムが機能し、冷却を続けることができます。 まず、圧力容器内の気圧が75気圧以上になるとSRV(逃がし安全弁)が開いて圧力容器から格納容器に水蒸気を逃がします。 次にHPCI(高圧注水系)とCS(炉心スプレー系)の2系統が作動し、復水貯蔵タンクや圧力抑制室の水を圧力容器に送って炉心を冷やすのです。
ところが、津波で非常用電源が壊れこのECCSも停止してしまいました。 ECCSがだめになったので、常に水の中に入れて冷やしておかなければならない圧力容器内の燃料棒が水から露出してしまい、原子炉はついに制御不能になった。 マスメディアはそう報じました。 ですから、みなさまもそのように思いこんでいたのではないかと思います。
でも、そうではありません。 実は「最後の砦」があったのです。 1号機では「IC」(非常用復水器)、2、3号機には「RCIC」(原子炉隔離時冷却系)という「最後の砦」があって、ECCSがダウンした後も、1号機のICは8時間、3号機のRCIC(とHPCI)は36時間(1日半)、2号機のRCICは70時間(約3日)動いて冷却を続けていたのです。 ECCSがだめになり、すぐに暴走が始まったわけではなかった。 ここが、まさに今日の課題です。 この「最後の砦」が動いている間に手を打てば、原子炉は暴走しませんでした。 そして客観的にみて、少なくとも3号機と2号機については、海水注入をする余裕がありました。 ところが、経営者はそれを拒んだ。 技術経営の底知れぬ愚かさと題する所以です。
わざわざ山を削って原子力発電所を海抜11メートルという低い位置に建設したこと、非常用電源のほとんどを地下1階に配置したこと、など、いわゆるリスクマネジメントの不備がさかんに問われています。 また1号機については、現場がICを止めてしまうなど、現場の失敗を、政府事故調などは糾弾しています。 もちろんこれらは重大です。 ところがこの原発事故の原因を考える時に、リスクマネジメントの問題や現場の失敗にばかり目を向けると、問題の本質を見誤ります。 本質は、リスクマネジメントでも現場の失敗でもない。 技術経営の過失なのです。 いまからそれを論証します。

原子炉の暴走の状況を調べる時...
測定された物理量について大事なものが3つあります。 第1に、圧力容器の中の「原子炉水位」。 これは、燃料棒(炉心)の露頭から測ることにします。 よってこの値はプラスでないといけません。 プラスなら、燃料棒が水に浸っていて炉心は制御可能の状態にある。
ところがマイナスになると炉心が水から顔を出すことになるので、とたんに制御不能となり、暴走して燃料棒のメルトダウンが始まります。
第2に、「圧力容器の圧力」。 圧力容器は、最大83気圧まで耐えられます。 先ほど申し上げたように、75気圧になるとSRVが作動し、中の水蒸気を逃すようになっています。 今回の事故ではこのSRVがきちんと作動したことが分かっています。
そして第3に、「格納容器の圧力」。 格納容器の耐圧は、3.8気圧です。 もしこの圧力が3.8気圧を大幅に超えてしまったら格納容器が爆発してしまいますので、このベントを手動で開ける。 こうして格納容器の爆発を防ぐようになっています。 ただし日本の原発では、ベントのあとに放射性物質をトラップするフィルターが付けられていませんでした。 とはいえ、原子炉水位がプラスであるあいだにベントを開ければ、周囲に放射線被害をほとんどもたらしません。 ところが原子炉水位がマイナスになって炉心の一部がすこしでも溶けた後にベントを開けると、放射性セシウムなどが外に放出され、多大な放射線被害をもたらします。 福島の悲惨はこうして起きました。 第一の「原子炉水位」がプラスであるうちにベントをして中の圧力を抜き海水注入をしていれば、この悲惨は免れたのです。
この3つの物理量をよく記憶しておいていただき、3号機ついで2号機がどのように制御不能になったのか、東電から官邸に送られたファクスを読み取って作り上げたデータを今から示します。
まず、3号機。
地震発生の後、11日の午後3時5分にRCICが手動起動されます。 その後、ECCSが津波で喪失した後もRCICは動き続けます。 作業員のミスで12日午前11時36分に停まりますが、HPCIがその1時間後に自動的に動きはじめ、こうして、13日午前2時44分まで1日半の間、3号機の原子炉は冷やされ続けました、原子炉水位は4メートルから5メートルで推移しています。 圧力容器の圧力もHPCIが起動した途端、75気圧ぐらいから一気に下がり始め、12日の午後には8気圧にまでさがりました。
ここで、みなさんは不思議に思われるはずです。 ならば、なぜRCICおよびHPCIが動いて原子炉水位がプラスであるうちに、海水注入をしなかったのか。 とりわけHPCIが動き始めたあと圧力容器の圧力は8気圧程度にまで下がったのですから、3月12日の夕刻から13日未明にかけては、ベントを開ける必要すらなく消防ポンプで容易に海水を入れられたはず。 なぜ海水注入の意思決定はなされなかったのか。
いっぽう2号機は、
RCICが約3日のあいだ炉心を冷やし続け、原子炉水位はその間4メートルを維持し、圧力容器の圧力は50気圧台から60気圧前後、格納容器も3気圧~約4.5気圧で推移しています。 3号機同様、この「制御可能」の間にベントを開くことも海水注入も行うことができました。
ところが東電の経営陣は、海水注入の意思決定をしなかった。 3号機も2号機も、「最後の砦」が停止し、原子炉水位がマイナスになってしまってメルトダウンが起きてから、ようやく海水注入を行なう意思決定をしています。 水位がマイナスになってしまったら、燃料棒が崩壊熱で溶け、放射性セシウムやストロンチウムが格納容器のほうに出てきて、ベントを開ければこれらが外界に出てしまって大変なことになる。
とりわけ3号機。 HPCIが動いて圧力容器の圧力が8気圧の時であれば、ベントをすることなく消防車で効率よく海水を入れられた。 そして暴走に至らなかった。 これらの情報は、すべて東電の経営陣にまで行っていました。
なぜ東電の経営陣は、ベント操作も海水注入も、原子炉水位がマイナスになり原子炉が暴走するまで、その意思決定をしなかったのか。
私は、昨年3月に、東電が逐次公表するデータ(さいわい官邸が逐次公表していました)をグラフにプロットしながら、この謎を解こうと思いました。 仮説は明らかです。 すなわち東電は2、3号機を廃炉にすることが嫌だった。 だから意図的に海水注入を拒んだ。 しかし、その仮説を主張してみたところで、東電経営陣が「いやいや、そんなことはない。 我々は最善を尽くした。 海水注入についても、原子炉暴走の前(原子炉水位がプラスであるうち)に意思決定した。 しかし結局のところ現場があわてふためいて混乱し、海水注入ができなかった」と主張すれば、水掛け論になってしまいます。 ここは実際に現場にいて「状況」を目の当たりにした方の証言がどうしても必要です。 しかしそのような証言者の発見は、まったく不可能でした。
しかし僥倖が訪れました。
昨年11月、菅直人前総理の側近として官邸で対応した日比野靖JAIST副学長から、メールが届いたのです。 日比野さんは管さんに乞われ、3月12日の午後9時から菅さんのそばにいて、そこで起きたことを見聞きしていたのでした。 そこで私はさっそく日比野さんにお会いしてインタビューさせていただきました。 資料に、日比野さんからのインタビュー録をそのまま載せています。 12日の午後9時ごろの話です。
菅さんは、東電の武黒一郎フェロー(当時)、原子力保安院院長、原子力安全委員会委員長に「3号機と2号機について、いますぐベントをして圧力を抜き、すぐさま海水注入すべきではないか」と何度も尋ねています。 日比野さんも、東電(原子力安全部長)から「海水注入のリスクはない」との答えを得たあと、「そうなら、なぜ早くベントと海水注入をしないのか」と言ったといいます。 これに対し、東電は、「ベントは、できるだけ粘って最後にしたほうがいい」と主張したそうです。 そして結局、HPCIが停止した13日朝、3号機は暴走してしまった、と証言してくださいました。 菅さんと日比野さんは「結局、廃炉にするのがいやなんじゃないのだろうか」と、考えるに至ったとのことです。
以上のお話をまとめておきます。
2,3号機は、津波で非常用電源が壊れECCSが動かなくなった後も、RCICは「最後の砦」となって動いていた。 最後の砦が稼働している間は、原子炉は「制御可能」の状態にあったわけで、この間に「ベントと海水注入」をしていれば「制御不能」の状態つまり「暴走」は起きなかった。 しかし、東電の経営者はこれを拒み続けました。
1号機は不可抗力であったかもしれません。 しかし今、示したように2、3号機では余裕を持って「ベントと海水注入」はできたはず。 ところが、東電は故意に拒み、その結果放射能汚染は6倍にもなったのです。
ではなぜ東電の経営者は海水注入を意図的に拒んだか。 それは、非常用電源が失われたらすぐ「ベントと海水注入」をやるのではなく、ぎりぎりまでねばってやるという「過酷事故マニュアル」に因る可能性があります。 しかし、1号機が未曾有の事態になった時、可及的速やかに3、2号機で海水注入を意思決定できたはずです。 にもかかわらず、東電の経営者は、暴走すれば人知を超える原子炉の「物理限界」とは何かが理解できず、意思決定を怠って原子炉を制御不能に陥らしめた。 福島原発の事故は、技術ではなく、実に東電経営者の「意志決定をしなかった」という「過失」に他ならず、よってその刑事責任は極めて重い、というのが私の主張です。
では、きょうの問題提起をしておきましょう。
去る5月28日に、国会事故調査委員会が、菅前総理の事情聴取を行ないました。 その中で、聴取にあたった野村修也氏(中央大学法科大学院教授・弁護士)は、「日比野靖氏という、原子力の専門家でない人間を官邸に呼び、福島原発の所長たちにさまざまな素人質問をさせたことで、現場を混乱させた」と主張しました。 日比野さんは確かにコンピューターサイエンスが専門ですが、若い時に物理学を修めた立派な物理学者です。 しかし、野村氏にしてみると、原子力工学出身で原子力工学の技術者ないし教授をしていない人は、すべて「専門家でない」のでしょう。
「原子力工学を修めた人以外は、この領域に踏み込むべきでない」という野村氏の意見について、みなさんはどうお考えでしょうか。 私は、この原発事故にしても、日本の原子力行政にしても、原子力工学を修めた人だけで、閉鎖的共同体(原子力村)を作ってしまったことのほうが本質的な問題なのだと思っております。 むしろ原子力村以外の科学者たちが大いに越境して問題解決に取り組むべきだと考えています。
野村氏は、国会事故調の事情聴取の場で、「管リスク」を声高に叫びました。
「菅さんが専門家でもないのに専門家ぶったことがこの事故を大きくした」というのです。 しかし、私は少なくともこの原発事故については、東電の撤退要請を断固として拒んだことで、菅氏は日本を救ったのだと思います。 東電の撤退要請に対して、政府や経産省の「専門家」は「撤退やむなし」と結論していたと聞いています。 しかし彼ら「専門家」にしたがって東電が事故現場から撤退していたら、いまごろ東京までも人の住めない地域になっていた可能性がある。 またすでに論証したように、3号機と2号機については、「専門家」こそが、過ちを犯しました。 菅氏は、残念ながらその専門家たちに異を唱えられなかった。 かくて海水注入がなされませんでした。
次に、過酷事故マニュアルです。
福島原発事故後も、原子炉の過酷事故マニュアルは未だに「RCICが稼働したら可及的速やかにベントと海水注入する」という手順(ノーマリーオフ原理)になっていません。 つまり、福島の事故と同じ事故が起こることが今でも「予約」されているのです。 ところがこの現状を、ジャーナリズムもアカデミズムも正そうとしないし、政府事故調、民間事故調、そして国会事故調もまったく言及しないのは、なぜなのでしょう。 私は、ただちに全原発の過酷事故マニュアルを「ノーマリーオフ原理」(直訳すると「通常はオフ」。 つまり異常が発生したときには必ず「オフ」して絶対に暴走しないように設計する思想。 エレクトロニクスでは常識)に変更。 そして、現場判断の場合は、海水注入を決断・実行した何人も免責となることを法的に保証することを提言します。 以上が徹底されて初めて40年未満の原発の再稼働が議論されるべきと考えます。 また、1号機と同じIC型原発はただちに廃炉とするべきだと考えます。
最後に、

JR福知山線事故と東電原発事故との両者が共通して抱えている「技術経営の誤謬」を超克するにはどうすればよいか、ということです。 その超克には、これまでに述べたように、分野横断的な課題解決能力が要求されます。 そのためには科学・技術と社会を共鳴させ「知の越境」を縦横無尽にしながら課題を解決する新しい学問の構築が必要だと考えています。 これについてもどうすれば実現するのかをご議論願えればと思います。 日本では、それぞれの分野の専門家の間には、その分野を踏み越えるべきではないという空気があります。 私はプロフェッショナルというのはそうではない。
堀場さんもよくおっしゃっているように、だれでも、その分野の8合目までは登れるはずです。 分野横断的に8合目まで登って、さまざまの分野の立場から議論を尽くしたいと思っております。